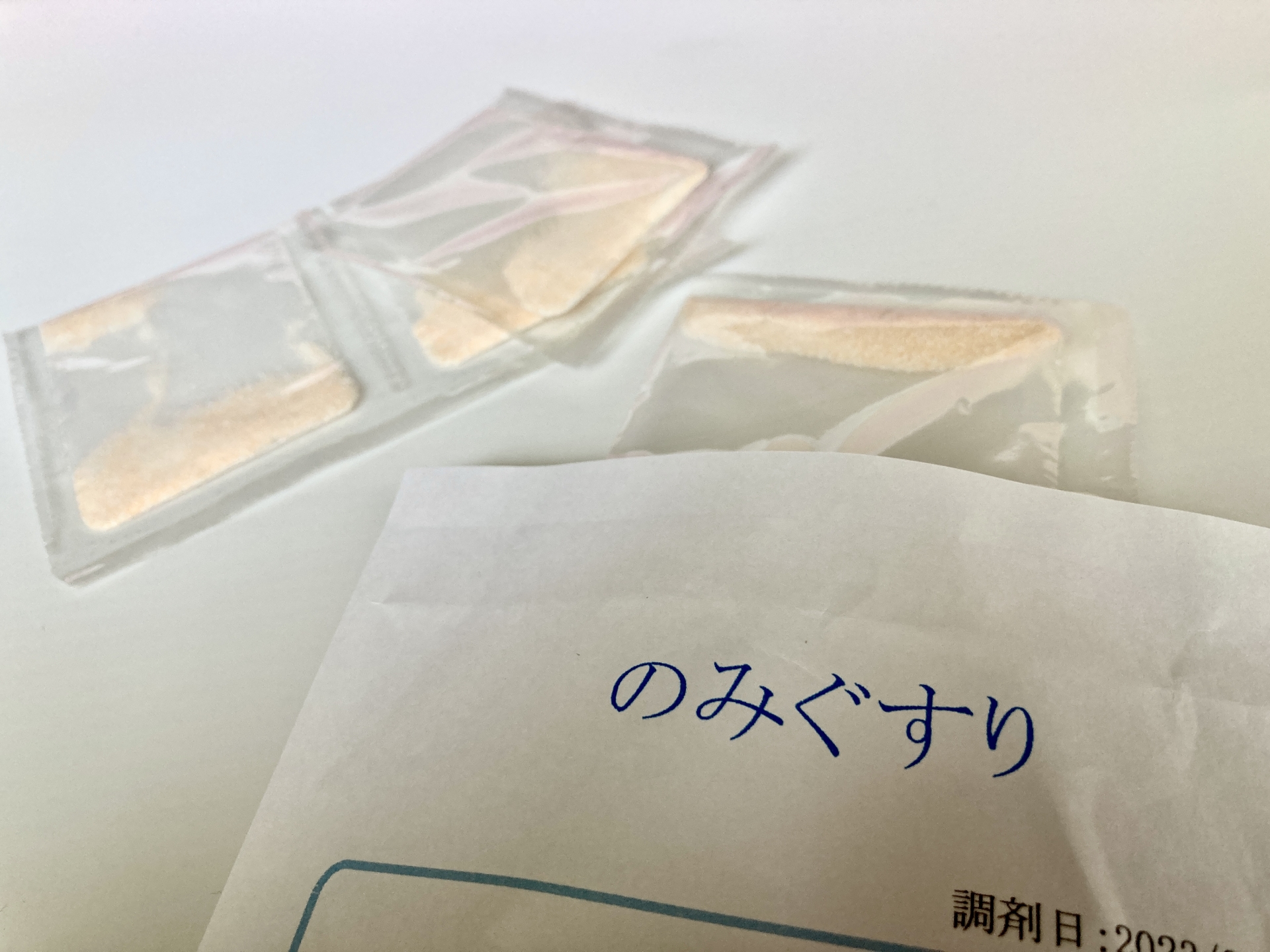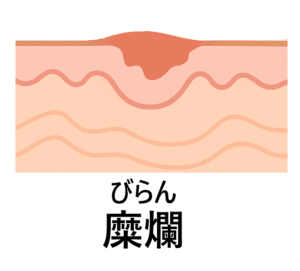お子さんに薬を飲ませるとき、思わず「苦い!」と嫌がられて困った経験はありませんか?
実は、小児科でよく処方される カルボシステインDS(去痰薬) と 抗生物質のDS を一緒に混ぜると、苦味が増すことがあります。(DSはドライシロップのことで、甘い味つけをした散剤です)
実際に薬局で調剤をするときにはカルボシステインDSと一部の抗生物質は一緒に混ぜないようにしたりしています。
今回は薬剤師の視点から「なぜ混ぜると苦くなるのか?」を分かりやすく解説します。
カルボシステインとは?
カルボシステインは、痰を切れやすくして排出を助ける薬です。
子どもの風邪や気管支炎でよく使われ、粉末状の ドライシロップ(DS) として処方されることが多くあります。
カルボシステインDSは、少し酸性の性質を持っています。この「酸性」が、後ほど苦味に関係してきます。
抗生物質DSの「苦味」の正体
抗生物質の中でも、クラリスロマイシンDS(クラリス)やエリスロマイシンDSなどのマクロライド系抗生物質は特に苦味が強いことで有名です。
もともとこれらの薬は
- 大きな環状構造(マクロライド環)
- 塩基性のアミノ基(ジメチルアミノ基など)
上記2つの構造をを持っていて、人間の舌の「苦味受容体」を強く刺激します。
そのままでは苦すぎて飲めないため、製剤としては 糖衣・甘味料・香料 でマスキングされています。
より詳しい説明をすると、大きな環状構造は脂溶性(疎水性)が高く苦味受容体のTAS2Rファミリーに結合しやすくアミノ基による静電的相互作用で結合が安定化しより強力に作用するためです。
なぜ混ぜると苦くなるのか?
① 酸性でマスキングが壊れる
カルボシステインDSは弱酸性。
その酸性によって、抗生物質DSに含まれる 糖衣や甘味料が溶けやすくなり、本来隠されていた苦味成分が表に出てきます。
② pH変化で薬が溶けやすくなる
マクロライド系抗生物質は「弱塩基性の薬」です。
酸性の環境では水に溶けやすいため、口の中で受容体に届きやすくなります。
その結果苦味を強く感じるようになります。
③ 香味のバランスが崩れる
カルボシステイン自体にわずかな酸味や硫黄系の風味があります。
これが抗生物質に添加されている甘味を打ち消し、相対的に苦味が目立つようになります。
特に注意が必要な組み合わせ
- クラリスロマイシンDS+カルボシステインDS(最も苦いと評判)
- エリスロマイシンDS+カルボシステインDS
- 一部のセフェム系抗生物質でも苦味が目立つケースあり
苦味を減らす工夫
- 服用間隔をずらす(混ぜずに別々に服用)
- 甘味シロップでマスキング(処方時に相談可能)
- 冷やした水で後追いすると苦味が和らぐ
- 無理に混ぜないで、疑問があれば薬剤師に相談する
まとめ
- カルボシステインDSと抗生物質DSを混ぜると苦味が増すのは、
「酸性でマスキングが壊れる+薬が溶けやすくなる」 のが主な原因。 - 特にクラリスロマイシンDSは苦味が強く、混合でさらに飲みにくくなります。
- お子さんが薬を嫌がるときは、自己判断せず薬剤師に相談するのが一番です。
薬をきちんと飲める工夫をして、治療をスムーズに進めていきましょう。
参考
医療用医薬品 : カルボシステイン
The molecular receptive ranges of human TAS2R bitter taste receptors
Bitter taste receptors
Extraoral bitter taste receptors as mediators of off-target drug effects
An update on extra-oral bitter taste receptors
クラリスロマイシンドライシロップと各種カルボシステイン製剤併用時の苦味強度における先発医薬品と後発医薬品間の違い
関連記事